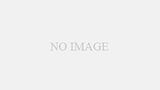はじめに
製薬企業がデータベース研究(以下、DB研究)を実施する際、自社の研究結果が「臨床現場での診療行動をどう変えるか」は、研究の重要な成果の一つだと思います。
いかに科学的価値のある論文であっても、臨床現場に携わる医師らの納得感を得られなければ、現場へ浸透させるハードルが上がってしまいます。
潰瘍性大腸炎治療の論文を題材にした前回記事では、医師の臨床現場感覚に合った内容を、データや数値をもって示すことで、医師に対して高い訴求力が得られることがわかりました。
今回は、糖尿病の合併症評価に関するDB研究の論文を複数の専門医に読んでいただき、感想をインタビューしました。そこで得られた知見から、製薬会社のみなさまの研究デザインやメディカル戦略に活かせるポイントを抽出しました。
調査背景
今回インタビューを行った医師
- 医師A:医歴15年、腎臓病・生活習慣病領域を専門とする大学病院勤務医。
- 医師B:医歴20年、糖尿病・腎臓領域を専門とする病院勤務医。
- 医師C:医歴25年、循環器内科、現在はクリニック副院長として一般内科外来を担当。
- 医師D:医歴20年以上、国の戦略研究や糖尿病対策推進会議にも関わる糖尿病専門医。
今回対象となった論文
JMDCレセプトデータを用い、糖尿病診療の質を経年的に評価した論文1を検討対象としました。2006〜2016年にかけて糖尿病治療薬を使用した患者を対象に、血液検査(脂質、腎機能、血糖値)の評価と眼科受診が適切な受診間隔で行われているかを調べた結果、特に遵守率の低い項目として、HbA1cの3か月ごとの測定(2015年時点で69%)、眼科受診(2015年で39%)が指摘されました。
本調査背景
糖尿病診療の現場では、ガイドラインで推奨される包括的な合併症評価が必ずしも実践されていません。特に網膜症評価は受診のハードルが高く、患者の理解不足や医療機関間の連携不足が要因とされています。今回の論文は、こうした「エビデンスとプラクティスのギャップ」を明らかにし、改善余地が大きい領域を定量的に示した点において、DB研究ならではの重要な知見といえます。
医師らのコメント
本論文で示されたギャップへの感想や想起した自身の診療経験
本研究で示された、糖尿病の合併症評価でのエビデンスプラクティスギャップはなぜ起きているのでしょうか?現場の医師に聞きました。
- 診療所でやっているので、眼科的評価はたしかに難しい。把握できていない。口腔内の衛生状態、末梢神経障害も評価が難しい。
- 日本の保険診療の問題点もあって、合併症の検査を医師側がやろうと言っても、費用が余計にかかる。短い診察の間で、(必要性を十分に)説明できない。
- 困っていないのに、余計お金を変える提案をされても、次にしてください、と言われる事が多い。『先生は薬だけ出してもらえればいい』という患者さんもいる。
前回記事で触れた潰瘍性大腸炎(UC)診療のエビデンスプラクティスギャップとして、主治医の専門性や経験が大きな要因として挙げられた反面、今回の論文に関しては、内科外来の多忙さや患者側のニーズなどの要因が多く挙げられました。ひとことにエビデンスプラクティスギャップといっても、ギャップの要因は疾患によって多様であり、臨床医にヒアリングして「なぜそのギャップが生じているのか」を具体的に理解することが、研究を現場に即したものにする第一歩となります。
医師が違和感を感じるポイント①:研究の対象患者集団と臨床でみる患者集団の年齢層のズレ
今回インタビューをした医師の多くが、本研究の対象患者の年齢層が実際にクリニックに来る自身の患者と比べて若い点に、違和感を感じていました。同じく対象集団の違和感として、入院患者や外来を中断しがちな患者を除外した点に対する意見も見られました。
- 対象の保険の関係で、高齢者が少ない。クリニックでは高齢者群が非常に多い。それがすっぽり抜けている。
- 実臨床では60歳以上が多い。そこはどうなっているのか?
- 今回の研究から、外来を中断しがちな人は抜けている。実臨床では「久しぶりに外来に来たと思ったら腎機能が悪化している」ような人がいる。
- 除外基準で外される人が多い。入院した患者が一律で省かれてしまっているのが難しい。
つまり、臨床現場では「しっかり通院し継続的に管理されている患者」だけでなく、「高齢で多疾患を抱える患者」や「外来中断を繰り返す患者」も多数存在し、それが診療の大きな特徴になっているということです。にもかかわらず、本研究ではそうした層が切り落とされているため、医師にとっては「自分が日常的に向き合っている患者像が反映されていない」という違和感につながりました。
したがって、糖尿病診療においてより臨床現場の状況にあわせるためには、若年層・安定患者だけでなく、高齢者や通院中断例を含めることで臨床に納得感をもたらすエビデンス提示につながる可能性があります。
また別の観点として、エビデンスプラクティスギャップの研究では、エビデンスが遵守されている可能性の高い患者集団を対象として実施し、「この患者集団ですら、エビデンスの遵守割合はXX%と低いです。アドヒアランス不良者や健康意識の低い人だと、状況はもっと悪い可能性が高いです。」というメッセージをつくることもあります。実際今回の研究はJMDCデータという健康保険組合由来のレセプトデータを使っているため、少なくとも同世代の患者群に比べると、社会経済的に恵まれていて、健康リテラシーも高い可能性があります。この観点に対する理解は医師によって差が大きかったため、研究リテラシーやデータベース研究への理解度に応じて、適切に研究背景/デザインを伝えることで、その研究をより正しく、有用に理解してもらえる確率があがります。実際にインタビュー中にそのような背景を伝えると、本研究に対する医師の納得感も向上しました。
医師が違和感を感じるポイント②:研究の対象患者集団と臨床でみる患者集団の臨床的背景(治療薬等)のズレ
本研究では注射薬(インスリンとGLP-1製剤)を使用している患者では検査施行率が良いことが示されていましたが、医師の意見として、使用している薬剤の種類や数による層別解析を見たいとの意見もありました。
- 単剤で治療中の人か、糖尿病薬を多剤併用している人かでも結果が変わってきそうだ。日本だと初手の薬剤選択がまちまちなので、単剤であっても何を内服しているかで結果が変わってくるのが気になった。
同じ「内服薬治療中」といっても、その背景には大きな差があります。単剤でコントロール良好な患者なのか、あるいは3剤を併用しても血糖コントロールが難しく、インスリン導入の瀬戸際にある患者なのかで、合併症評価の必要性や診療上の優先度はまったく変わってきます。したがって、患者背景を層別化する際には、使用薬剤数や種類といった治療段階の違いを把握することも重要であり、これが反映されてこそ臨床に納得感をもたらすエビデンスになります。
医師が違和感を感じるポイント③:隣接するClinical Questionへの好奇心
さらに、医師らの意見では、検査施行の有無だけでなく、疾患発症や死亡などのイベントを評価したいとの声も聞かれました。
- 実際、心血管イベントなどのハードアウトカムも見たかった。
- 心不全や腎不全などの合併症を拾ってもよかったかもしれない。
題材となった論文は「診療の質評価」を主目的としていたためハードアウトカムは対象外でしたが、臨床医としてはやはり患者のアウトカムを知りたいという思いが強いことが伝わってきました。JMDCデータベースには併存症のICD-10コードも含まれており、このようなアウトカム研究をデザインすることも十分可能です。
なぜハードアウトカムが重視されるのか。それは、医師にとって重要なのは検査を「実施したか否か」よりも、「その検査によって患者にどれだけのメリットがあるのか」だからです。 例えば、「HbA1c検査の実施率が何%か」という数字よりも、「HbA1cを3ヶ月ごとに測っている患者の方が心筋梗塞リスクが低い」といったハードアウトカムが提示されるほうが、臨床現場での納得感は格段に高まります。しかし一つのデータベース研究に複数のClinical Question/Research Questionを入れ込むことは推奨されません。そもそも、臨床医も自らが抱くClinical Questionに対して、最新のエビデンスを常に把握できているわけではないです。本研究に対して抱いたような隣接するClinical Question/Research Questionについては、十分なエビデンス/既報が存在することも多いです。臨床医の納得感を向上させるためには、本研究に隣接するエビデンスや既報を適切に伝えて該当するデータベース研究の位置づけ/意義を整理して伝えることが、より深く納得感を生み出すことにつながります。
研究の位置づけを正しく理解することで、医師は患者に対しても「検査をすることで将来の合併症を防げる」と具体的に説明でき、患者の受診行動や治療アドヒアランスを変える力となります。ひいては、こうしたアウトカム提示が診療行動の変化につながり、エビデンスプラクティスギャップを埋める研究デザインの一助になると考えられます。
自身の診療への振り返り
- 実臨床していると、絶対測っている。私自身やっていることは、まともなことをやれていたんだな、と思った。これだけの患者さんが、評価されていないことを考えると、患者さんの不利益になる。
- 自分自身の施設の診療を振り返ると、十分に手当できない検査(例えば網膜症、腎症)がある。抜けていることはしばしばある。
これらの声からは、DB研究が単なる数値の提示にとどまらず、医師にとって「鏡」のように機能していることがわかります。自分の診療行動を客観的に見つめ直し、抜けている部分を認識するきっかけとなっているのです。こうした振り返りは、ガイドライン遵守やエビデンスプラクティスギャップの解消につながる第一歩といえます。DB研究は単なる現状把握にとどまらず、現場の診療行動を内省的に見直し、改善につなげるきっかけを与えるものといえます。
臨床現場に訴求力のある治療実態研究を実施するためのポイント
このインタビュー結果から、より臨床現場に訴求力のある治療実態研究を実施するためのポイントを以下にまとめました。
医師が違和感を感じるポイントへの対策は?
医師からは「対象患者が実臨床と比べて若い」「外来中断例や入院患者が除外されている」「重症度や治療段階が十分に見えてこない」といった違和感が指摘されました。これらは、研究デザインや背景説明を工夫し、臨床の現実にあわせたり、既存のエビデンスを整理して本研究の位置づけを明確にすることで改善できると考えられます。
DB研究を現場に近づけるためには、臨床が現状どのような課題を抱えているのかを正しく理解し、その上で適切なClinical Questionを設定し、研究が臨床に与えるインパクトを見極めながらデザインすることが不可欠です。
本研究の例での「臨床が抱える課題」とは、多くのクリニックでは高齢で多疾患を抱える患者が多く、外来を中断する患者や、入院のたびにADLが低下していく患者が日常的に存在することです。さらに「内服管理」といっても、単剤でコントロール良好な患者もいれば、多剤併用でもコントロールに難渋している患者もいます。加えて、「お金がかかる検査は避けたい」という患者の希望や、短い診療時間の中で説明しきれない現実も存在します。こうした多様な背景を無視して「検査がされていない」と一括りにするのでは、臨床医には響きません。
したがって、適切なClinical Questionとは、単に「検査率が低い」という事実を提示することではなく、「どのような患者集団で、どのような理由で検査が実施されていないのか」を丁寧に切り分けることです。そして、そのうえで「どの層の医師に、どのようなメッセージを届けたいのか」を明確にする必要があります。
医師の学びや内省を深める方法は?
今回のインタビューを通じて明らかになったのは、医師は研究論文を読むことで自身や自施設の診療を真摯に振り返り、内省を深めているという点です。本研究を読んだ医師からも「自分の施設でも網膜症評価は十分にできていない」「クリニックでは合併症評価まで手が回らない」といった声が挙がり、DB研究が“自分の診療を映す鏡”として機能していることがわかりました。こうした振り返りは、まさに学びや内省を促進するうえで効果的だったといえます。
医師の内省をさらに深めるためには、研究を単なるエビデンスの提示にとどめず、臨床現場で「使える」キーメッセージを発信することが重要です。今回のインタビューでは、医師から「自分の患者層ではどうか」「クリニックではこういう事情がある」といった意見が多くみられました。したがって、研究結果を現場の状況や患者層とより緊密にあわせることが、内省を一層促すうえで有効だと考えられます。
さいごに
リアルワールドデータを使った研究は、現場の治療実態を描出し、“たまたま受診した医療機関や医師によって診断や治療が全く異なる”というエビデンスプラクティスギャップを調査するのに非常に適しています。
このような臨床現場に即した研究は現場に強い訴求力を持ちますが、臨床医にとって納得感のある形で提示するには、臨床実態を深く理解したうえで、対象読者となる医師を正しく想定し、現場に即したメッセージを届ける工夫が必要です。
データックは、臨床と疫学をつなぐ架け橋として、製薬企業が“臨床現場に届く研究”を実現できるよう支援します。みなさまと共に、DB研究を臨床に真に活かされる形で生み出し、エビデンスプラクティスギャップの解消に貢献していければ幸いです。
DB研究でお困りの際は、ぜひ一度データックへご相談ください(ご相談・お問い合わせはこちら)。
参考文献
- Tanaka H, Sugiyama T, Ihana-Sugiyama N, Ueki K, Kobayashi Y, Ohsugi M. Changes in the quality of diabetes care in Japan between 2007 and 2015: A repeated cross-sectional study using claims data. Diabetes Res Clin Pract. 2019 Mar;149:188-199. doi: 10.1016/j.diabres.2019.02.001. Epub 2019 Feb 8. PMID: 30742858.