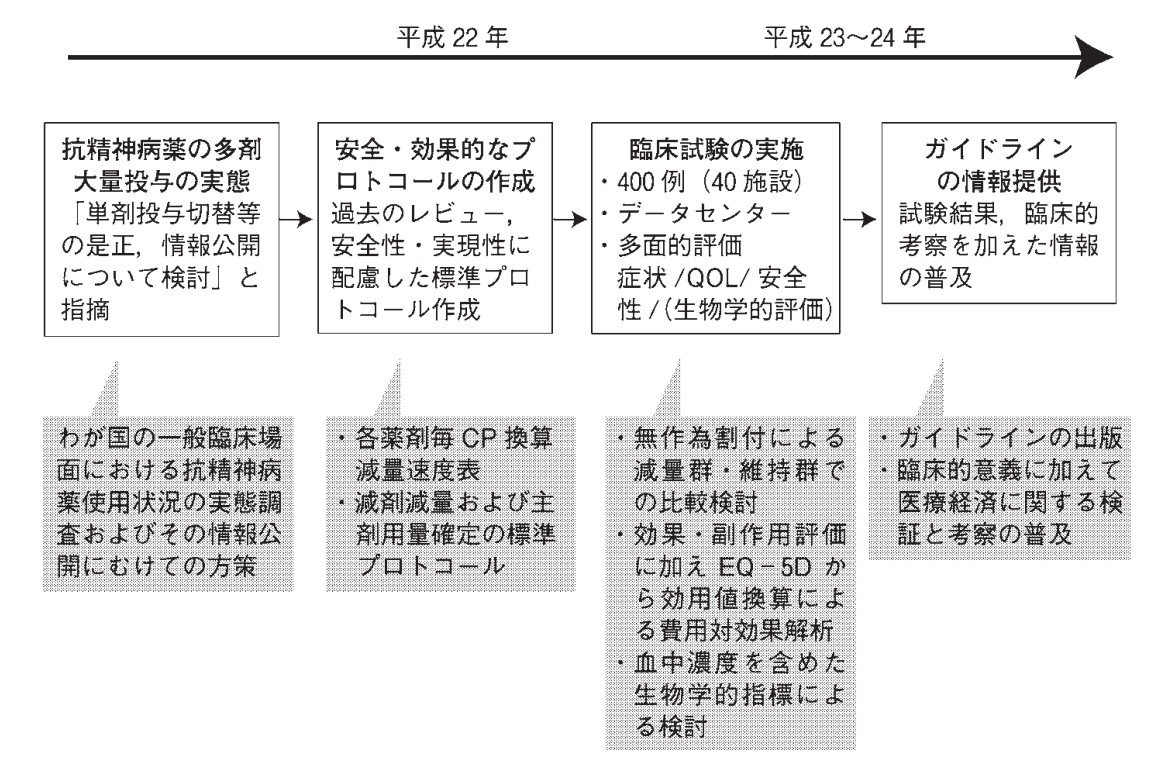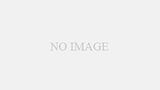はじめに
製薬企業がデータベース研究(以下、DB研究)を実施する際、自社の研究結果が「臨床現場での診療行動をどう変えるか」は、研究の重要な成果の一つだと思います。いかに科学的価値のある論文であっても、実臨床に携わる医師らの納得感を得られなければ、現場へ浸透させるハードルが上がってしまいます。
データックは、エビデンスプラクティスギャップの可視化や解消に向けて、どのような研究をデザインし、メッセージを作れば臨床医への訴求力が高まるかを調査・検討しました。
今回は、潰瘍性大腸炎(UC)に関するDB研究の論文を複数の専門医に読んでいただき、感想をインタビューしました。そこで得られた知見から、製薬企業のみなさまの研究デザインやメディカル戦略に活かせるポイントを抽出しました。
調査背景
今回インタビューを行った医師
- 医師A:医歴30年、大学病院および海外大学で指導歴のある肝臓内科医
- 医師B:医歴25年、大学病院にて消化器内科・外科の両方の指導を行っている外科医
今回対象となった論文
潰瘍性大腸炎(以下、UC)患者におけるステロイドの使用実態を検討した論文1を対象としました。JMDCレセプトデータベースを用い、2006〜2016年にUC治療薬を開始した7907人を対象に後ろ向き解析しています。研究結果として、2011年に生物学的製剤が登場して以降ステロイド使用は減少したものの、2016年時点でも34.3%が180日以上の長期ステロイド使用を継続していたことが示されました。
本調査背景
UCの治療は、生物学的製剤の登場によって大きく変化しました。現在のガイドラインでは、生物学的製剤を中心とした治療が推奨され、副作用の多いステロイドは短期間に限るべきとされています。しかし、現場では依然としてステロイド長期投与が行われているというエビデンスプラクティスギャップが、本研究により可視化されました。
医師らのコメント
本論文で示されたギャップへの感想や想起した自身の診療経験
まず、本研究で示されたエビデンスプラクティスギャップは、なぜ起きているのでしょうか。医師らの意見によると、以下のような場面が想定されます。
- ある程度の年齢の医師、特に自分が研修した時になかった薬で、診療所や一人医長で情報が入っていない場合などは、生物学的製剤に抵抗感がありそう。(ステロイドの少量長期投与は)ガイドラインで推奨されていない。(ステロイドの容量や生物学的製剤を)躊躇した使い方をして、結果的に(ステロイド使用が)長期化している。
- 地方だと、UCを専門で診ている先生が近くにいない場合もあり、患者さんに交通手段がないと生物学的製剤を使える先生に通えない。
これらの意見から、UC治療におけるエビデンスプラクティスギャップを考察する際には、患者背景を整理するだけでなく、治療を担う医療機関の種類やアクセス環境まで含めて検討することが不可欠であるとわかります。
医師が違和感を感じるポイント:対象患者の層別化
医師が本研究について違和感を感じた点として、以下があげられました。
- 患者の組み入れ基準としてICD-10コードを用いている点に関して:UCは診断が難しい。初期像はクローン病様で、検体病理で判明することがある。
- どのくらいの重症度の患者が集まっているのか明らかになるといい。(レセプトデータでわかる重症度指標として)手術の有無があったらよかった。
- 「大学病院で治療に難渋したうえでステロイドが長期投与されている患者」と「医師側要因で最適でない治療を受けている患者」を分けて考える必要がある
同じ“長期投与”であっても背景は大きく異なり、医師としてはそのような多様な背景・重症度・併存症の患者を一括りにすることに違和感があるようでした。臨床的に意義のある併存症や患者背景についての情報をより詳細に描出し、層別化して分析することで、臨床に納得感をもたらすエビデンスを提示することができます。
自身の診療への振り返り
医師らが感じた自身の診療への振り返りとしては、以下のコメントがありました。
- そうだろうな、という内容だった。それを目に見える形にした。結果は腑に落ちるような感じだった。
- 他施設や他の医師と比較して、自分の診療がどう位置づけられるかを考えさせられた。(自分の患者でも)他院で治療している人がステロイドをずっと飲んでいる…患者さんは、他の治療法を知らない。
このように、医師は研究論文を通じて自身や自施設の診療を真摯に振り返ることがわかります。そしてその内省をさらに深めるには、研究を「どう届けるか」が重要です。数字を示すだけでなく、背景や前提を揃え、キーメッセージに注力することで、医師の学びや行動変容へとつながります。
臨床現場に訴求力のある治療実態研究を実施するためのポイント
このインタビュー結果から、より臨床現場に訴求力のある治療実態研究を実施するためのポイントを以下にまとめました。
医師が違和感を感じるポイントへの対策は?
医師からは「診断の妥当性に問題がありそう」「重症度が見えない」「施設分布が不明」といった点に違和感が示されました。これらは、レセプト・DPCを使った研究の限界としての側面が大きいですが、研究デザインの工夫や背景説明による補いをしっかり行い、研究をより臨床現場にあわせることで改善できる可能性はあります。と考えられます。
本研究に限らない一般論ですが、「診断の妥当性に問題がありそう」や「重症度が見えない」への対策として、
- 対象患者を入院患者や特定の検査や治療(手術等)を実施した患者に絞り込むことで、診断の陽性的中度を向上させたり、重症度を揃えたりする
- 指定難病フラグを利用する
といった手法が有用なこともあります。
一方で、上記のような絞り込みによって対象患者集団は狭まり、患者数も減少するというデメリットもあるので、研究の目的・キーメッセージに応じた研究デザインが大切です。
医師の学びや内省を深める方法は?
本インタビューを通じて、医師は研究論文を読むことで、自身や自施設の診療を真摯に振り返っていることがよくわかりました。こうした内省は、医師の診療を改善するための第一歩であり、研究の持つ大きな意義でもあります。
この学びをさらに促進するには、研究を単なる数字の提示にとどめず、臨床現場の課題や文脈に結びつけて伝えることが欠かせません。数字の背後にある患者像や治療環境を描き出すことで、医師は自らの診療と重ね合わせながら理解し、行動変容につなげることができます。そのためにはまず、DB研究を実施する側の臨床理解が必須です。最終的にエビデンスを使う医師がどのような現場に立ち、何を課題と感じているのかを的確に捉える必要があります。そして、研究結果としての論文化で終わらせず、その先にある「エビデンスをつたえる・つかう」までを見据え、誰にどのように届けるかを逆算した研究プロジェクト設計が求められます。
さいごに
リアルワールドデータを使った研究は、現場の治療実態を描出し、“たまたま受診した医療機関や医師によって診断や治療が全く異なる”というエビデンスプラクティスギャップを調査するのに非常に適しています。
このような実臨床に即した研究は現場に強い訴求力を持ちますが、臨床医にとって納得感のある形で提示するには、臨床実態を深く理解したうえで、対象読者となる医師を正しく想定し、現場に即したメッセージを届ける工夫が必要です。
データックは、臨床と疫学をつなぐ架け橋として、製薬企業が“臨床現場に届く研究”を実現できるよう支援します。みなさまと共に、DB研究を臨床に真に活かされる形で生み出し、エビデンスプラクティスギャップの解消に貢献していければ幸いです。
DB研究でお困りの際は、ぜひ一度データックへご相談ください(ご相談・お問い合わせはこちら)。
参考文献
- Matsuoka K, Igarashi A, Sato N, Isono Y, Gouda M, Iwasaki K, Shoji A, Hisamatsu T. Trends in Corticosteroid Prescriptions for Ulcerative Colitis and Factors Associated with Long-Term Corticosteroid Use: Analysis Using Japanese Claims Data from 2006 to 2016. J Crohns Colitis. 2021 Mar 5;15(3):358-366. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa172. PMID: 32845311; PMCID: PMC7944504.